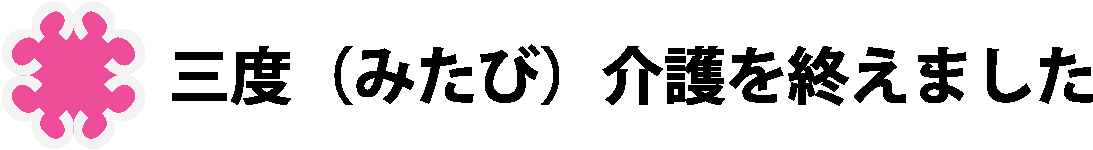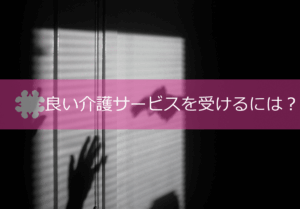当ウエブサイトをご訪問してくださる方のなかには、在宅介護と仕事の両立に悩む人も少なくないのではないでしょうか。私も、つい昨日のように思い出しますが、今から12年以上も前、実母の在宅介護が始まった当初、経営している会社の社名を変更するなど、経営方針を変えました。
だからといって、仕事を犠牲にしたとは思っていません。会社としてもターニングポイントだったに過ぎません。そもそも、ワークライフバランスは、家庭では、その営みへに責任と、社会では職務への責任、それぞれを高次元で成り立たせる取り組みです。
仕事で手を抜いて、家庭でのんびりする行為ではありません。
誰でも他人の仕事にプロフェッショナルを求めている
鉄道に乗車したところ考えてみましょう。
もし、運転手がアマチュアだったら、その車両に乗りたいですか?
答えは、ノーのはずです。
他にも、地域医療を支える病院に急患でお世話にならないといけない状況を考えてみましょう。
担当してくれるドクターが育児休暇かなにかで、医学部の学生しかいないとしたらどうしますか?
そもそも、地域医療は崩壊していますよね。
場合には、行政に文句を言っているはずです。
このように、世の中のあらゆるモノやサービスは、それらを提供する専門家やプロフェッショナルによって支えられていますが、逆に言えば、私たちは常にプロフェッショナルにより提供されるモノやサービスを求めます。
つまり、誰がおこなうワークであっても、それは常にプロフェッショナルでないと通用しないのが「社会」なのです。
ワークとライフで何をバランスするのか?
「ワークライフバランス」という言葉の意味は次のように捉えている人も多いのではないでしょうか?
「仕事はそこそこ。家庭は楽しく。」
違っていたら申し訳ないとは思いますが、中らずと雖も遠からずのところでは、この行動規範が、都合の良いバランスではないでしょうか?
では、そんな心構えのドクターが、病院で勤務していたとしましょう。
そのドクターは、真剣に、命懸けで、あなたの病気を診断してくれると思いますか?
私は、絶対にそうは思いませんね。
仕事をお願いする相手というのは、常に忙しいけれども確実に成果をアウトプットしてくれる人に限ります。
これは、絶対にそう思います。
では、そのような人が、いわゆる世間で怠け者がすがる「ワークライフバランス」を意識するとでも思いますか?
私は、絶対にそうは思いません。
要するに、本当の「ワークライフバランス」とは、家庭であれば家族の営みに100%の責任をもち、社会であれば職務に100%の責任を持つ姿勢です。
ですから、本来、「ワークライフバランス」を大切にと言われれば、「それは責任重大ですよ」、という意味で使われなければ、怠慢を誤魔化す言葉にしかなりません。
在宅介護と仕事の責任を100%果たす。
年老いた親御様を在宅介護すると言っても、その中身はご家庭の状況によって様々です。
しかしながら、細切れになっていく自分の時間は、共通していることでしょう。
その時間をどれだけ充実させられるのかがポイント、というのが私の経験です。
また、在宅介護と仕事というように分けて考えているうちは、上手くいかないとも思っています。
例えば、英語習得でビジネス英語だとか、旅行で困らない英会話だとか、いろいろな切り口で英語学習が紹介されていますが、その根本には、基礎の文法、ボキャブラリーの充実というのが先に無いと話になりませんよね。
それと同じように、在宅介護も、仕事も、自分の人生の上に起きている対処・対応しなければいけない現実でしかありません。
その根本には、生きるとは何か?、という根本的な問いが隠されていて、その問いに応えていくための取組が、在宅介護であったり、仕事であったりということに過ぎない事実が見えてきます。
逆に言えば、在宅介護や、仕事への真剣な取り組みが、生きるという行為そのものであり、それが一体、何かという答えを掴む結果に行き着くのです。
なので、わざわざ、在宅介護や、仕事と分けて捉えて、それらのバランスを取ろうとしているうちは、何も見えず、何も掴めないのです。
人生に起こる全ての出来事に全力でぶつかって責任を取るように努めてください。
それが、ワークライフバランスです。
家庭では老いや病の家族の在宅介護に責任を持ち、そして社会では職務の責任を全うする。これが本当のワークライフバランスのあるべき姿です。
その大変さを表に出さず実践してきたのが、2025年10月4日に選出された自由民主党の新総裁です。その新総裁がワークライフバランスを捨てるとまでおっしゃるほどに、その地位は重圧なのだろうと慮ります。
しかし、やがてその地位の相応しさを纏い、さらなる高次元のワークライフバランスを表に出さずに実践されるのではないかと期待しています。
長寿社会時代をどの国よりも早く実現した日本だからこそ、静かに示すこの時代に敵った後ろ姿は、次代に続く者への模範となるのではないでしょうか。