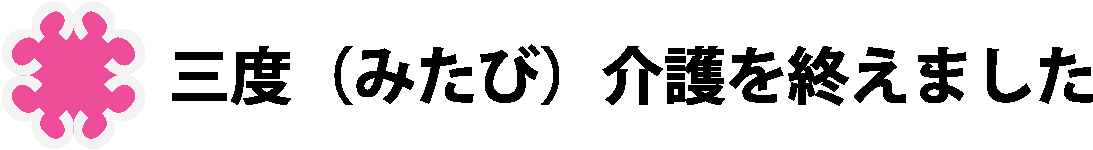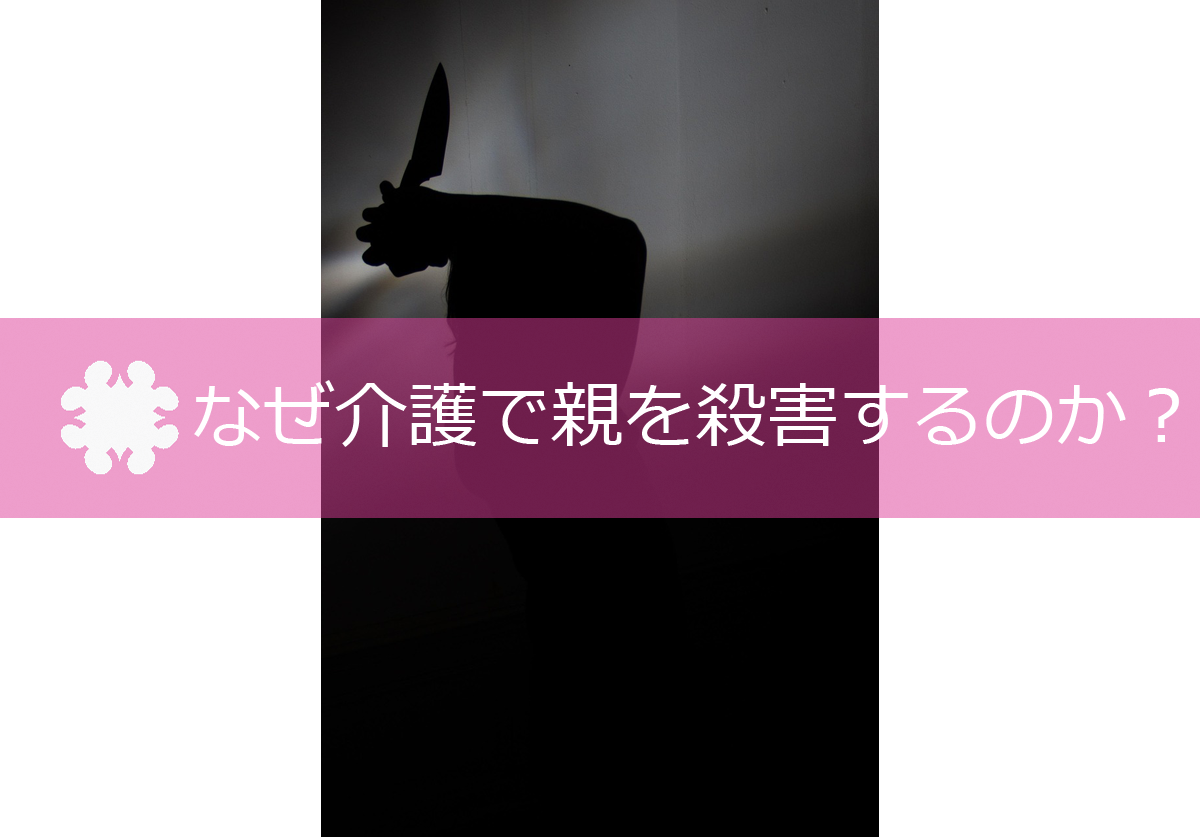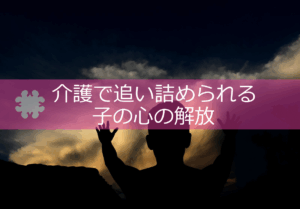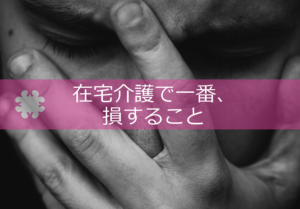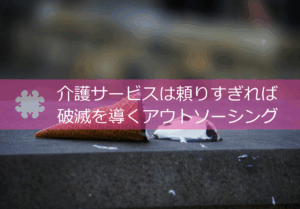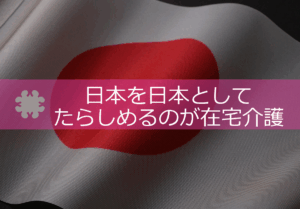介護する子が年老いた親御様を殺害する事件が後を絶ちません。そもそも、親を殺害する、もしくは自死を選択する理由から学ばないといけません。まず、その行為が異常です。しかし、殺害してしまう。
地球を俯瞰してみても、自ら命を絶つ生命は、人間だけ。親を殺害する生命も、ほぼ人間だけなのです。
しかし、その時、すでに人の心は失っています。
介護と殺人
介護する子が、どうして自殺するのか。
介護する子が、なぜ、親を殺害できるのか。
一言でいえば、心が追い詰められます。
追いつめられるとは、どういうことか。
≪ 生きられない ≫
この感情に支配されます。
「生きられない」感情・・・・・。
それって何か判りますか?
ここが重要です。
そもそも、生命が生命として存在するための原動力は、「生きたい」という欲の感情と、「死にたくない」という怒りの感情です。
この2つの感情が生きる原動力です。
潜在意識がどうのこうのという話もよく見かけますが、潜在しているのにどうして潜在していると判ったのかが不思議な意識でもあるのですが、それはさておき、心を看破すると、「生きたい」という欲の感情と、「死にたくない」という怒りの感情しか見えてきません。
ひとつ、例を挙げましょう。
ハエが飛んでいるとして、ハエ叩きなどで殺そうとしてください。
ハエは、どのようなアクションを取ると思いますか?
そうです、ご存じの通り、これまでのスピードをはるかに超える常軌を逸した速度で、予想できないモーションを繰り出し、逃げ切るはずです。
そりゃそうです、命がかかっているのですから、ハエも必死です。
「生きたい」し、「死にたくない」ですから。
つまり、欲と怒りの感情を最大限に発揮して、理性ではなく、本能の感情に従うままに、ハエは逃げ切ります。蜂であれば、攻撃してくるでしょう。
この感情の動きは、人間も同じです。
「もう、これ以上、生きられない・・・。」
そう思い詰めたところで起動する感情は、欲と怒りですから、それに飲み込まれた時、その原因対象を本能のままに攻撃します。蜂と同じです。
自死についても、原因対象を攻撃できないと判断した時、本来であればまだ生きられるであろう時間のエネルギーをすべて使い、自らの命を終わらせます。
個人支援と環境支援
親を殺害してしまう、もしくは自死を選択する感情のメカニズムを説明しました。
現実には、このメカニズムに陥る前に対応、対処、対策が必要になります。
というのも、年老いた親御様の在宅介護では、いい大人が自分の親を殺害します。
または、いい大人が自死の選択をします。
実は、ここに大きな特徴があります。
若年層で、学校でのいじめ、職場での嫌がらせによって、殺害される、自死を迫られる状況とは異なり、いい大人が犯行に及ぶのです。
十分に社会での経験を積む機会があった大人が、間違った道を選択してしまう。
ここを踏まえる必要があり、「明日は我が身だ・・・」と恐れるのではなく、そうならないためにどうすれば良いのかを学ぶ時間とチャンスがいくらでもあるという観点を逃してはいけません。
つまり、≪ 大人のための介護教育 ≫が何よりも重要だ、と気づく必要があるのです。
この内容が、間違いなく欠けてしまっている。
なので、まず大人のための介護教育を施していく≪ 個人支援 ≫がはじめにありき、です。
具体的には、親御様が介護が必要になる前から、それを学び、心構えを作っていく必要があります。
親御様が終活だと宣って、エンディングノートなど書いても意味がありません。
その介護教育の中では、現在の日本の介護サービス支援環境をどう利用していくのか、それはほんの一部の要素でしかありませんが、その利用ノウハウも考えていきます。
この介護サービス支援環境を整えるのが≪ 環境支援 ≫であり、ここは行政の出番となっていきます。
いま、子が年老いた親を殺害するといった痛ましさが報道されると、すぐに国がなんとかしろとか、行政がなんとかしろ、といった声が上がりますが、全くの見当違いです。
まず、在宅介護を基本として、それをしっかりと担えるように、≪ 大人のための介護教育 ≫を実践し、その教育を踏まえたうえで、既存の介護サービス支援環境を上手く使える力を、介護する子供自身が身につける必要があるのです。
個人の身上、心情、事情に他人は踏み込めない
年老いた親御様の在宅介護で痛ましい事件を生じさせないためには、まず国や、行政の介入は限定的、というよりはむしろ限界がある、と覚えておきましょう。
そもそも、ケアマネージャーが介入できるのは、親御様が要介護認定受けてからなのです。
そこから、初めて長寿化社会の現実を知ったというのでは遅いのです。
なぜなら、すでに親御様が要介護状態で、仮に認知症に罹患していたとすれば、意思疎通を図るのさえ難しい状況の可能性もあるのですから、親も、子も、納得のいく在宅介護のある日々を過ごせる選択肢は狭まります。
また、ケアマネージャーの介入があっても、介護を担う子のライフスタイルをどうにかするような具体的な支援は期待できません。そもそも、要介護の親御様への適切だと判断する介護サービスの紹介とケアプラン作成が彼らの仕事です。
ですから、介護する子の悩みを聞いて、相談に乗るような業務はケアマネに期待できません。
逆に言えば、介護する子の身上、心情、事情に踏み込んでくるような人は、介護する子にとってどのような人じゃないといけないと思いますか?
少なくとも、ケアマネージャーとのお付き合いの期間は、要介護が認定されて、親御様が亡くなるまで。
そして、彼らのキャリアは、介護業界に特化して構築されてきているケースがほとんどです。
当たり前ですが、若いケアマネージャーであれば、ご自分の親の介護すらやったことが無い人なんて、ごちゃまんといるのです。
介護する子にとって、年老いていく親御様の在宅介護の機会に接するとはどういうことのなのか???
そんな超基本的なことすら、ケアマネだったら明確に答えられるとでも思いますか?
親御様が年老いていくのが判っているのですから、介護する子は、まず、ここから学ばないといけないのです。
最後に一つだけ、明確な事実を申し上げれば、子供自身が、年老いた親御様の面倒を看るという心構えの醸成は、人間として真の自立を促します。
この意味を徹底的に知るところが、≪ 大人のための介護教育 ≫の出発点なのです。
年老いた親御様の在宅介護で痛ましい事件が生じてしまう最大の原因は、家系にそれまで息づいていた年老いた親を在宅介護する伝統と文化が分断され失われているからです。
戦後、右に倣えで地方から上京し、挙句の果てには東京に通勤時間1時間、2時間をかけてマイホームを建て、核家族化が当然のごとく生活し続けた結果、家系として伝えるべき背中を代々に伝承しなくなったためです。
なぜ、この地球上で人間だけが年老いた親御様を介護する生命として存在するのか?
一瞬でも良いから、考えてみてください。もし、本当にあなたが在宅介護で年老いた親御様が子に殺される現実が痛ましいと思うのであれば。