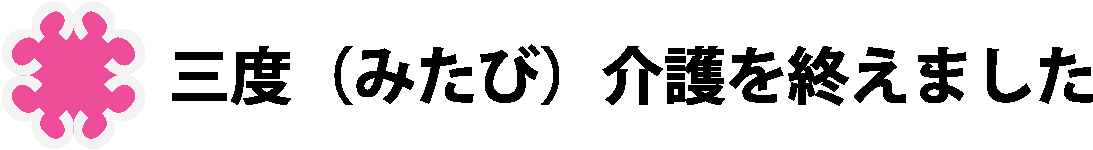2025年7月– date –
-
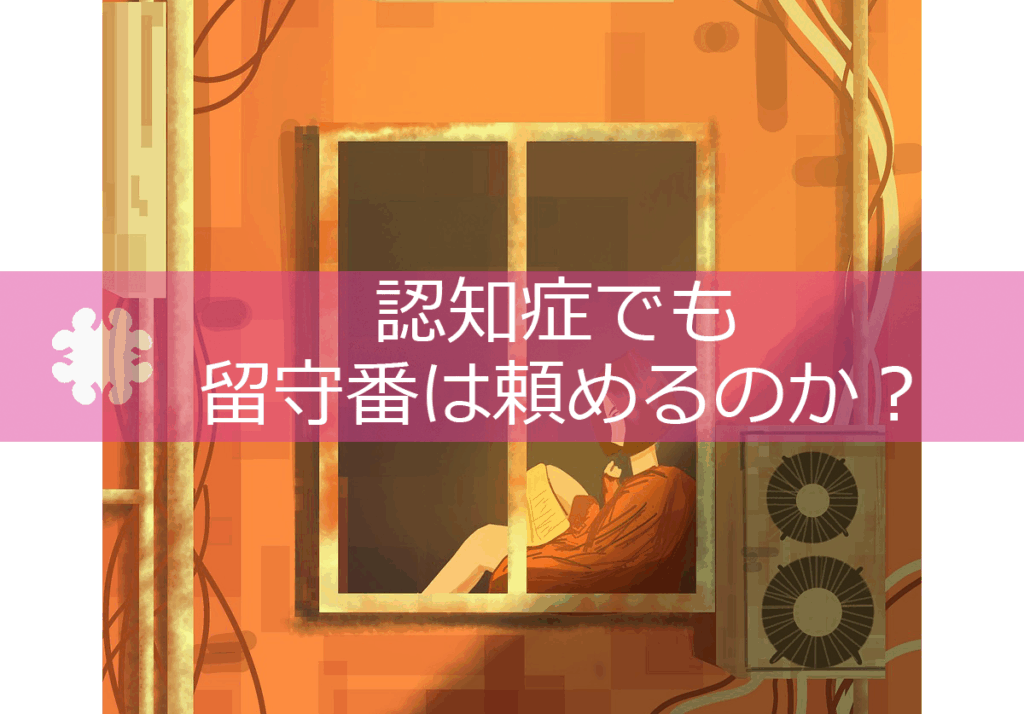
認知症でも留守番は頼めるのか?
結論から申し上げると、難しい。私の在宅介護では無理でした。在宅介護のある暮らしが軌道に乗るまでには、さまざまな失敗を乗越えます。その一つに、どこまで母に一人で留守番をお願いできるのか、という課題が生じました。例えば、大雪が降り、帰宅困難となって家内を夜に迎えにいかなくてはいけない状況がありました。時間にしておよそ30分程度ですが、この程度の時間であれば問題なく留守番はお願いできました。しかし、半日、一日と留守番をお願いすると、さまざまなアクシデントが伴います。 -

選挙と在宅介護
2025年7月の参議院議員選挙が終わりました。投票率が高くないと民意が反映された結果とは言い難いのは、私が言うまでもないことです。一方で、長寿の方々の投票行動は、総務省の年代別投票率をみると70代以上で括られてしまっています。年齢を重ねるほど、投票行動も大変になるのが現実ですが、在宅介護ではキチンと支援していく必要があります。なぜなら、投票権を勝ち取った歴史を検証すれば、支援は当然との思いに至ります。 -

日本を日本としてたらしめるのが在宅介護
第2次世界大戦後の核家族化の風潮により、「代々」という言葉が陳腐化してしまったのは日本にとって大変なデメリットです。少子化が問題であり、長寿化はめでたいことなのに、長寿化の言葉は差別的な高齢化という言葉に置き換わり、少子高齢化が問題とメディアでは吹聴されています。逆に言えば、長寿化社会を実現できるまでに成熟した国であるにもかかわらず、これを良しとせず、問題視しかしないので子を持つのを躊躇します。長生きはリスクでしかない。その狭小なヴィジョンから抜け出せないから少子化なのです。 -
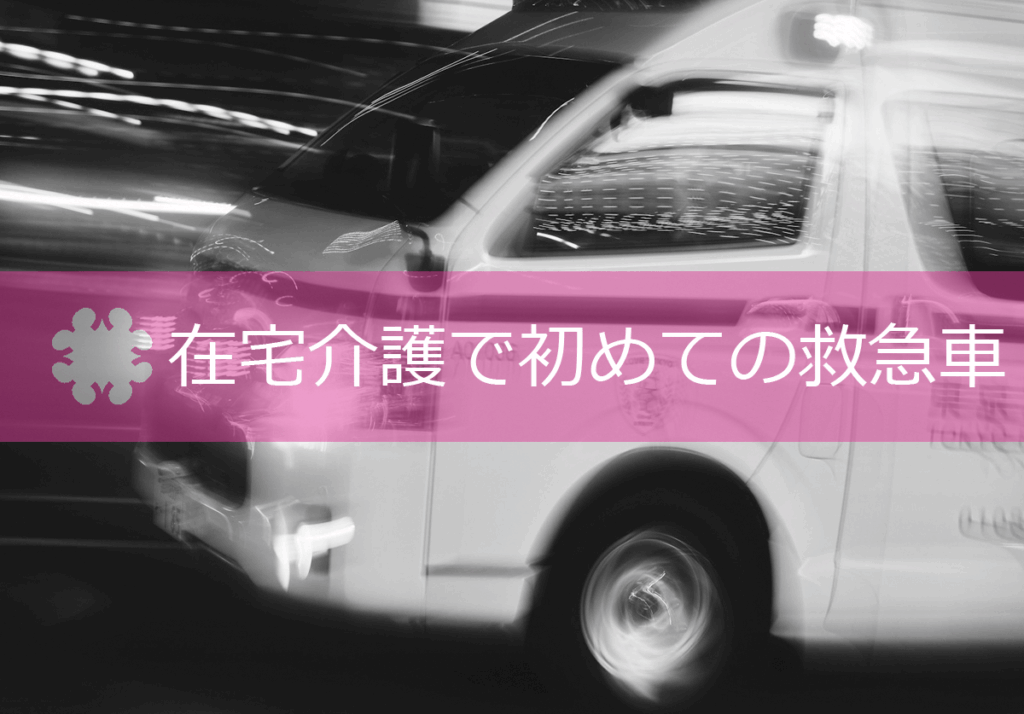
在宅介護で初めての救急車
年老いた親御様の介護に責任を持つ大変さの一面には、親御様の健康状態の変化に左右されるところでしょう。今日は元気でも、明日には具合が悪くなり寝込んでしまう。これが老いの現実です。いつまでも、いつも元気なままでいてほしいと願ったところで叶いません。この変化への対応力、幅が、在宅介護のクオリティを左右しますが、最初はそんな対応力は、皆無に等しいものです。さまざまなアクシデントを乗越えていく経験が、その実力を高めます。
1