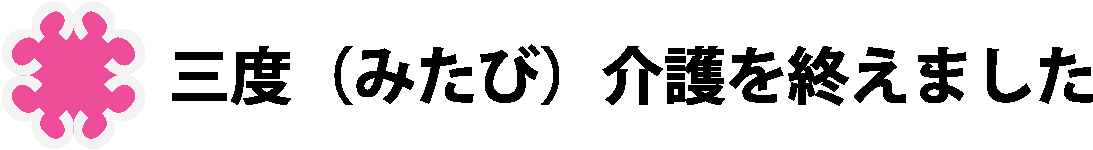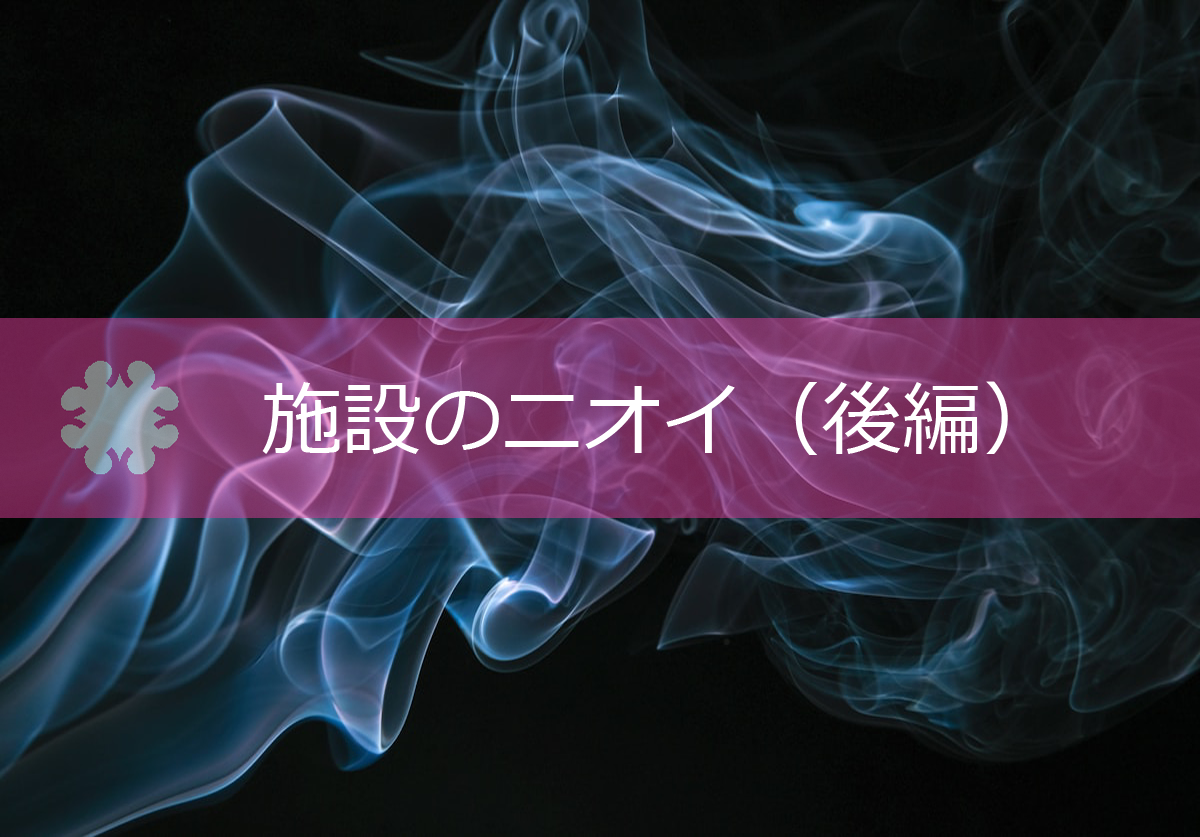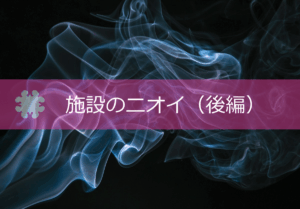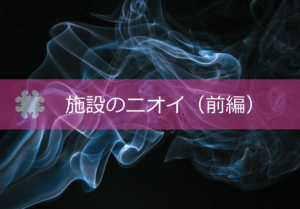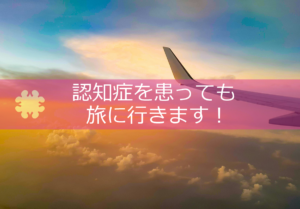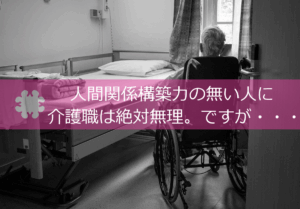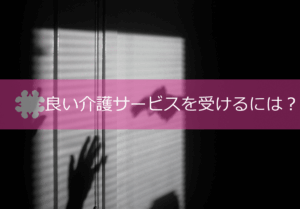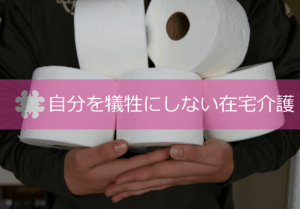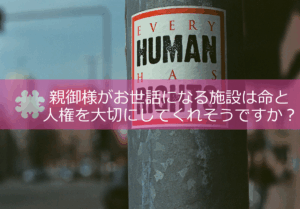特養のショート・ステイに1泊をお願いしたまでは良かったのですが、実際に母を連れて施設に伺ってみると・・・。
もし、初めてこの記事にご訪問くださった方は、『施設のニオイ(前編)』から目を通してくださるのをお勧めします。
それでは、続きを始めていきましょう。
翌日の午前中に母を迎えに行きました・・・
特養の施設から申し送りで伝えられた時間に、母を迎えに行きます。
前日に着ていた外出着に再び着替えさせてもらっていて、宿泊用の荷物もまとめら、母はベンチに座っていました。
他にもお迎えを待っているのでしょうか。
他にもご高齢の方が同じベンチに腰かけているので、少しおしゃべりに花が咲いています。
そこへ私が迎えに来たわけです。
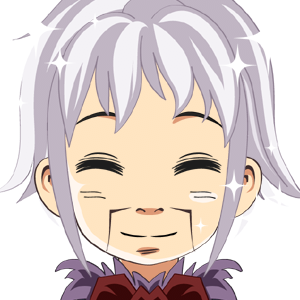 さくらの母
さくらの母お~、けんちゃん、来た来た
明るいトーンで言葉を発していましたが、表情がどこかぎこちなかったのをよく覚えています。
職員の方がお見えになって、ショート・ステイが無事に終了したことを告げられます。
そして、母を連れて大きな玄関を出て、特養をお暇した瞬間です。
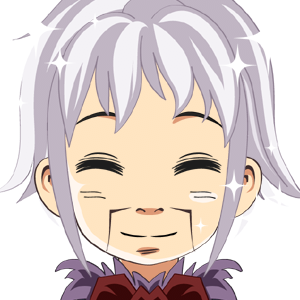 さくらの母
さくらの母もう、二度とこんなところは来たくない!
やっぱりなぁ、という感想が私の心にすぐに浮かびました。
よくよく話を聞いてみると、とても怖かったというのが理由です。
では、その怖さの原因は何だと思いますか?
施設に預ければ安心なのは介護する側の気持ちだけ
私も、30代の頃は介護というものに興味もなければ考えを巡らせる機会もありませんでした。
ですから、年取って助けが必要になれば、日本には介護保険もあるから大丈夫だろうという楽観的イメージが考えを支配していました。
しかし、実際に母の在宅介護をするようになって、その考えは180度という方向性だけでなく、さまざまな面で問題が存在するのが判ってきました。
例えば、認知症を患って要介護3をもらって特養に入ったとしましょう。
その認知症は、きっと良くなるに違いないと思って親を預けるなんてしないですよね。
- 手に負えない。
- だから、一生をそこで終えて欲しい。
その本音で、親を預けるはずです。
では、逆にもしあなたが認知症を患って、子供や親せきから特養に入ってくれと言われたらどう思いますか?
もちろん、身寄りもなく、独居で、誰の支援も無く、認知症やその他の重い病を抱えれば、施設は最後の砦です。
なくてはならないものです。
しかしながら、認知症は、そもそも脳に生じた疾患であって、心は罹患しません。
ですから、子供のために親の自分が犠牲なれば施設に入るのも仕方ないと強く思い込まない限り、積極的に入りたいなんて、心では思わないものです。
介護する側は、それを理解した上で親を入所させるか否かを判断しないといけません。
それでも個室に入れれば良いですが、多床室に入所するとどうなるか。
私の知っているその施設では、多床室の間仕切りはカーテンのような形でした。
夜の時間帯となり、職員の数も減りますから、認知症や重い病を患った多くのご長寿の方々が大人しく就寝してくれれば、事なきを得る一夜となります。
しかし、現実はそうではなりません。
奇声をあげられる方々。
寝たきりで排泄のため、職員の方々が奮闘しなくてはいけない状況。
そして、フロア内を徘徊される方々。
その特養は、フロアも多数階ありましたから、多くのご高齢の方々が入所されています。
仮に、ひとり、二人のご高齢の方が、奇声をあげたり、排泄介助を必要とされるなら職員の方々の奮闘で、ケアも行き届くでしょう。
ところが、実際は同時にさまざまな問題が生じます。
ある利用者の排泄介助をしながら、同時にほかの利用者の徘徊をとめるといったケアは無理があります。
このような環境の中で母が経験した恐怖は、夜になり徘徊する他の利用者が、母のベッドのところに来て、いきなりカーテンをガーッと開けられたとのこと。
これは、認知症を患っていても、ビックリするを通りこして、恐怖を感じます。
母曰く、なにかされるのではないかと恐怖を感じ、相当に身構えたようです。
それも一度ではないとのこと。
当然、職員の方に訴えても、その現場を見るわけではなく、再び徘徊していくその利用者をその人のベッドに誘導するぐらいしかできません。
また、ずっと見張っているというわけにもいきません。
それが限界であり、認知症が悪化して徘徊する方に、他人のベッドのカーテンを開けるなと注意しても意味がありません。
その日は、昨晩の恐怖体験を聞きながら自宅に連れて帰ると、母はすぐに横になって寝てしまいました。
よく眠れなかったと言ってましたから。
認知症になったら周囲からどのような接し方を望みますか?
私には、産まれたばかりの頃から懸命に育ててくれた両親がいます。
口にはしませんが、多大な、そして返しきれなかった恩があるといつも思っています。
母が患ったことで認知症という病に初めて接しましたが、だからといって母に変わりはありません。
認知症を患って最も苦しいのは誰かと言えば、母です。
介護する側の苦労話は、多く聞かれます。
ネットで検索すれば、山のように出てきます。
しかし、実際に認知症を患った方の気持ちは、表に出にくいものです。
想像してみて欲しいのです。
今日は何月何日と聞かれても、判らない気持ちを。
その苦しさをイマジネーションできますか?
もし、今のあなたが、明日になったら日付が判らず、住んでいる場所も判らないとなったら、とても苦しいはずです。
認知症になったら、判らなくなったらその判らない苦しみすらも判らなくなると思いますか?
答えは、ノーです。
心では、その苦しさがわかっています。
だから、問題行動が生じます。
認知症の問題行動は、その苦しさの訴え、というのが私の認知症症状観察による見解です。
その状態で、施設に入るという気持ちはどうなのか?
施設入所がダメだという見解は持っていません。
そこは勘違いして欲しくないのです。
ただ、その前にやるべきことはある。
恩返しとはそういうものではないでしょうか?
近未来の日本は人口減少すると言われています。
確かに少子化は問題だと思う反面、それはそれで良いのではないかと思います。
東京で10坪前後の土地を買って、ペンシル住宅を建てたところで高齢になって使い心地が良いかどうか。少し頭を使えば、答えは判りきっています。ですから、減少したら減少した最適解の国や地域を作れば良いのではないですか?
介護でも同じです。
近未来、人口減少したら今と同じような介護サービスは日本では提供されなくなるのではないかと心配する声を聞きます。
どこまで、わがままなのかと呆れます。
そもそも、不安や心配で生きるのはやめたらどうですか?
そもそも介護サービスは受けるつもりはない、そんな心意気が当たり前の世の中の方がよほど健全なのが判らないのでしょうか?
それでも、万が一の時は公の介護サービスがある。
そのような社会にしたいものです。