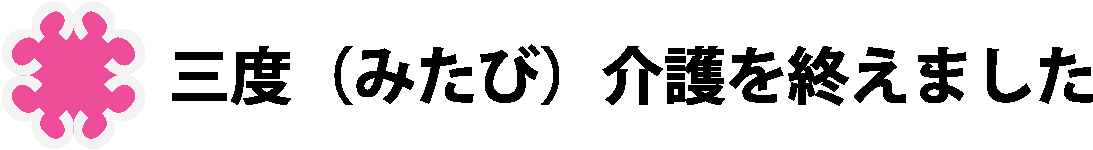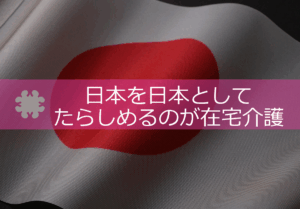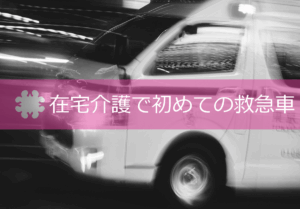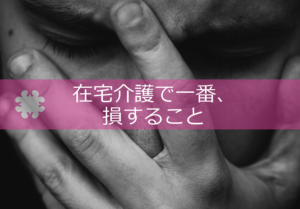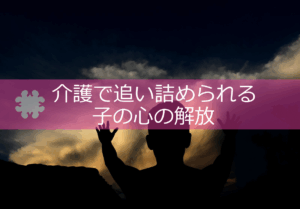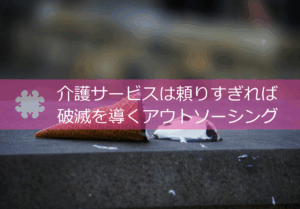第2次世界大戦後の核家族化の風潮により、「代々」という言葉が陳腐化してしまったのは日本にとって大変なデメリットです。
少子化が問題であり、長寿化はめでたいことなのに、長寿化の言葉は差別的な高齢化という言葉に置き換わり、少子高齢化が問題とメディアでは吹聴されています。
逆に言えば、長寿化社会を実現できるまでに成熟した国であるにもかかわらず、これを良しとせず、問題視しかしないので子を持つのを躊躇します。
長生きはリスクでしかない。
その狭小なヴィジョンから抜け出せないから少子化なのです。
代々が崩れる
第2次世界大戦後に、なぜ核家族化が進展したのか。
簡単です。
親の面倒を看ないで済むからです。
理由は、自分の仕事、自分の生活、自分の家族、自分の・・・などなど。
他にも、自由、夢、願望実現といった、ふんわりとした言葉に踊らさせれ都会に移住して核家族化が進みました。
こじつけでもいいから「自分の」都合を言い訳にして、さらにはわざわざ故郷を捨てて、遠くの街に移り住めば、親の面倒を看なくてすみます。
世の中の大多数の勘違いを質しておきましょう。
年老いた親の面倒や介護より、いわゆる企業等々のお仕事の方が、はるかにはるかに楽ちんです。
例えば、みんな大好き公務員や、みんながしがみつきたい大企業では、大失敗でもしなければ来月も、再来月もお給料がもらえます。
でも、年老いた親御様が認知症を患ったので介護離職して在宅介護をしようものなら、ダブル・ムキュウ(無休&無給)です。
だから、核家族化は、親の面倒を看なくてすむ便利なエコ・システムなんです。
親は年齢を重ねて認知症にでも罹患すれば、施設に送ってしまって、今の子供の生活は安泰です。
もし、日本を弱体化させようとする輩がいたならば、彼らの狙いはここにあったと言えるでしょう。
それが平成、令和と続く日本を弱体化させてきた要因です。
つまり、代々を崩されたのです。
代々が崩された代償は、ボディー・ブローの痛みに似ています。
失われた30年という言葉を聞きますね。
それは、平成という時代は、全く成長しなかったという意味です。
昭和は、あれだけ高度経済成長したにも関わらず、です。
戦後は焼け野原になったから成長した?
冗談なら判りますが、違います。もし、焼け野原がデフォルトなら、アフリカはどこの国でもとっくに経済成長しています。
昭和と平成では立役者が違う
かつて日本を代表し、世界を席巻した企業の一つにソニーという会社があります。
すでに、ソニー・ブランドの先進性を中国で紹介しても、鼻で笑われるだけです。
昭和の輝きは、平成になって凋落し、令和の現在では今のところ消えています。
昭和を築いたファウンダーの精神性を、平成の世となり、引き継げなかったからです。
ソニーを例にとりましたが、企業に限りません。
家庭でも同じです。
精神性を引き継げない理由を、家庭を例にとってみてみましょう。
大切な故郷を捨てて、核家族化の風潮に乗った結果、どうなったか。
日本人により捨てられた街は、外国人が拾う街へと変わっていませんか?
治安が悪化し、日本が失われていく実感がありませんか?
確かに政治の問題だと言える側面はあるでしょう。
しかし、その前に故郷を守るのは、その場所を故郷と呼べる人ではないですか?
故郷とは、自分が産まれた場所であり、自分が生まれる前から親が守り続けてきた場所です。
親は誰でも、やがて老います。
命懸けで子を守ってきてくれた存在である親ですが、いつかは子が守るべき存在へと変わります。
それが老いですが、老いは確実だと理解していれば、故郷を守るというのは、まず自分の親を守るという思想が最初に来るはずです。
それは、長寿化社会の現代では、在宅介護のアクションそのものに他なりません。
つまり、在宅介護は逃げてはいけない取組であり、その高い意識が故郷を守り、治安の悪化を防ぎ、やがて国防へとつながります。
死を知らない。だから伸びない。
なぜ、戦後、Japan As Number One と言われるまでに日本は成長したのか?
これも、答えは簡単です。
しかし、自分のものとして腑に落ちている人は少ないでしょう。
それは、多くの親友や仲間が、戦火に散っていったからです。
20代そこそこの年齢で、弾丸飛び交う最前線に赴き、命を落とす。
そのような親友を多く持つ人が、たまたま命を落とすことなく終戦後を生きなければいけないとなったら、どのような志、意識、情熱をもって時代を創造すると思いますか?
お受験だけが生きる支えのエリートの人ほど、自らの手で自らのこめかみに拳銃つきつけるぐらいの気持ちで、一度、よく思いを馳せてみてください。
戦争はやってはいけないことですが、だからといってその志を引き継ぐことなく、ましてや葬り去ることは、それ以上にやってはいけないことです。
なぜなら、戦争はやってはいけないというフレーズは、道徳のテキスト上の学びです。
これは、間違ってはいません。
しかし、戦火に散っていったおびただしい数の親友の死を偲び、志を引き継ぎ、死んでいった親友たちが羨ましいと思える豊かな日本を創造し続ける取組は、学びではなく、戦後を生きることになった人の義務であり、命懸けの超実践です。
つまり、戦火に散った親友の死を自分のものとしてマスターしたところに、日本の成長の原動力があったのです。
だから、戦後、Japan As Number One と言われるまでに日本は成長しました。
この超実践を継続するのが、間違いのないアクションなのです。
逆に言えば、この超実践の怠りが、日本を弱体化せていきます。
道徳のテキスト上の学びと、命を落とされた方々の意志を継ぐ超実践を区別しなければいけません。
例えば、この区別をつけるように指導するのが、初等の義務教育です。
同時に、戦争を遠ざけていることの出来ている日本で、実践的に死をマスターする機会から逃げてはいけません。
その機会が、年老いた親御様の面倒を看る在宅介護です。
親は、自らの天寿と引換えに、介護をする子に死を諭し、マスターさせます。
親の面倒を看るというのは、実践的に死をマスターする唯一無二のチャンスです。
なので、若くして親御様の介護をする人ほど、介護を終えた後の人生に飛躍する秘めたパワーを宿します。
それは、戦後の歴史が教えてくれています。
年老いた親御様の在宅介護の実践が冷ややかな目で見られる時代は終わりました。
むしろ、親の介護から逃げ出した子に対する社会の評価はかつてないほどに厳しくなります。
福祉は大事です。しかし、その言葉を隠れ蓑にして利権を貪る時代は終わります。
なぜなら、これからの時代は、親御様の在宅介護に真剣に取組み、親の天寿を通じて子は死をマスターする。
これにより限られた生への集中がバツグンに深まります。それを体現する人が増えていくからです。
そもそも利権って、なぜ生まれるかご存じですか?
死にたくないと生にしがみつく性根が利権をつくります。
なので、利権は死臭が漂うのです。