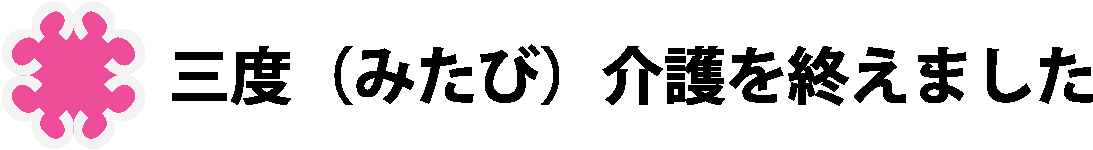トイレ– tag –
-

いつか旅行に連れていくの?
年老いた在宅介護でもっとも後悔するのが、やろうと思っていながらやらず仕舞いにしてしまった計画です。その最たるものが、旅行ではないでしょうか?年老いた親御様を連れて旅行にいくのは、しんどい面もありますが、もしやらなければその後悔は残り続けます。この記事を読んでくださったあなたには、その後悔は避けるのをお勧めします。 -
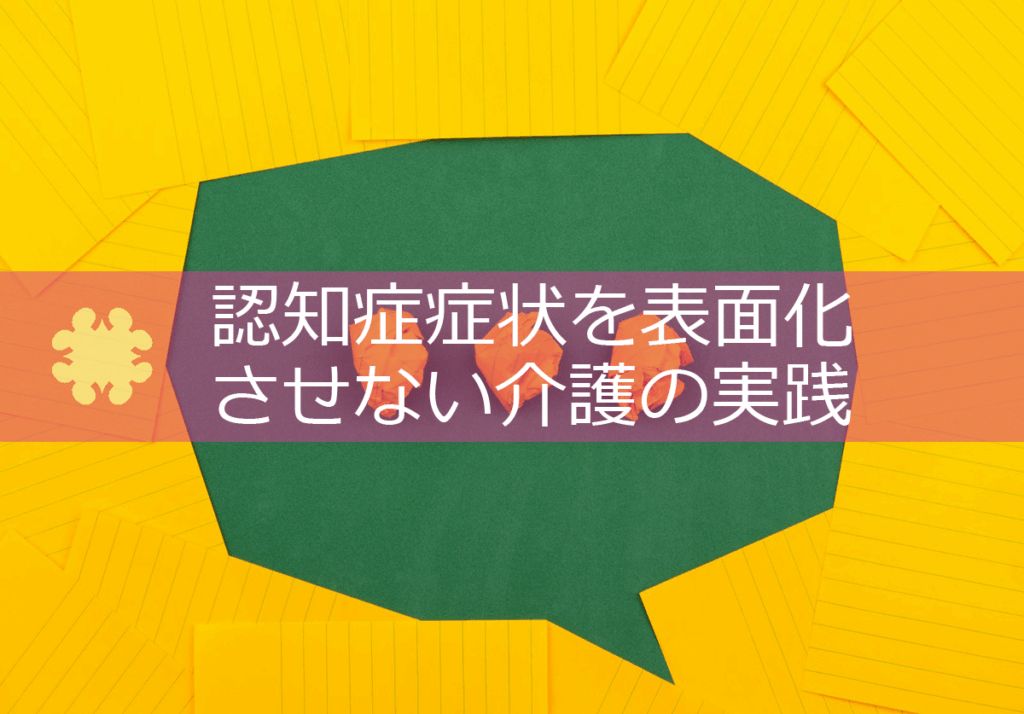
認知症症状を表面化させない介護の実践
認知症に罹患してもしなくても、あまり恐れる必要はないというのが私の経験則です。なぜなら、認知症は、脳の疾患であって、心は認知症にはなりません。心がしっかりしていれば、コミュニケーションも難しいものではない。認知症を患った実母の在宅介護実践と観察結果です。その理由?簡単です。コミュニケーションの基本は、「心を通わせる」。これに尽きます。 -

認知症による要介護3のコミュニケーション
認知症を患って要介護3と聞くと、どのようなイメージを持ちますか?老後に一人で暮らすのは、ちょっと難しいかもしれません。なので、年老いた親御様を在宅で介護するようになります。しかしながら、コミュニケーションが取れなくなるかといえば、十二分に可能です。コミュニケーションが取れれば、普通に親と子の暮らしが成立ちます。でも、それが出来ないのはなぜか?認知症により要介護3であった私の母とのコミュニケーションから解き明かしましょう。 -

在宅介護にマインドフルネスー身体の動作に気づくー
毎朝のルーティンとして、ティッシュペーパーによる折り鶴が日課になった岳母。マインドフルネスの≪気づき≫の実践を抵抗感なくクリアしてくれました。≪折る、折る、・・・≫自分の動作への気づきが出来るようになると、日常生活のあらゆるシーンに応用できます。例えば、キッチンで包丁を片手に野菜を切るシーンはやりやすいと思います。≪切る、切る、・・・≫実は、このマインドフルネスの気づきの実践は、転倒防止や、体調がすぐれない時にも応用できます。 -
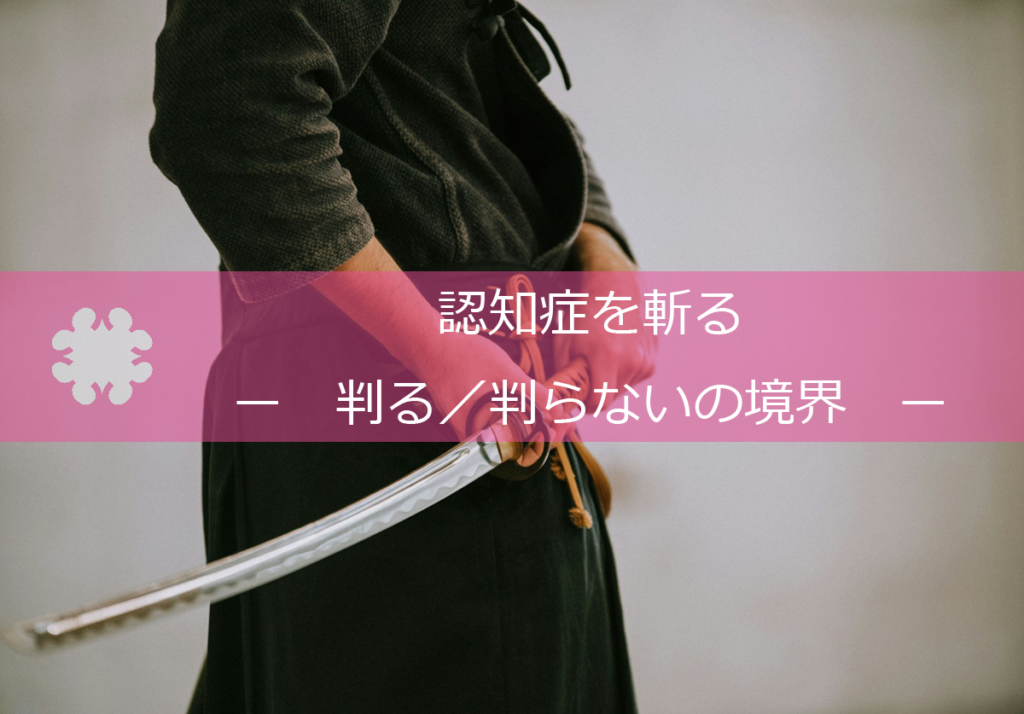
認知症を斬る―判る/判らないの境界―
認知症に罹患すると何も判らなくなると思われがちですが、違います。発語ができる健康状態で話をしてみると昔のことは覚えていたり、今、感じている嫌なことは嫌とハッキリとした意思表示もされます。もし、認知症が何も判らなくなる病気であれば、こうはなりません。ポイントは、判らなくなるところ、判るところ、その境界が明確にある認識と見定めです。
1