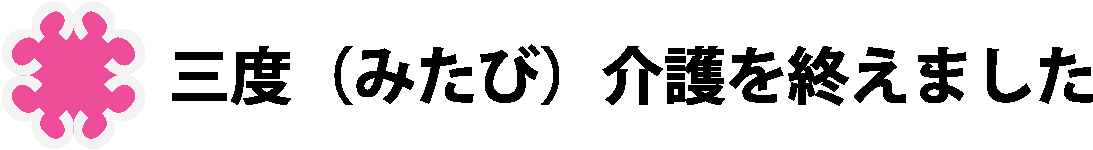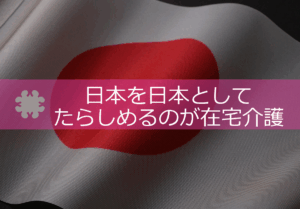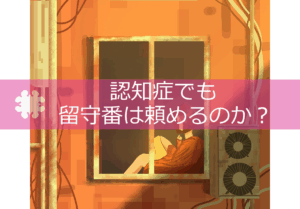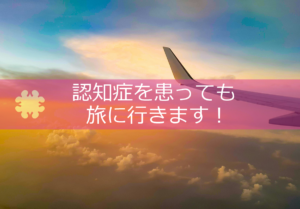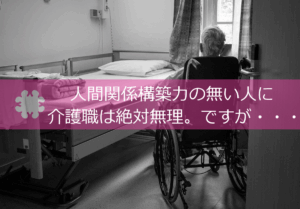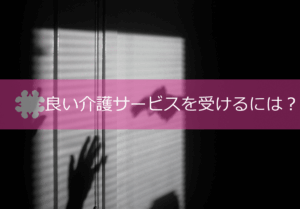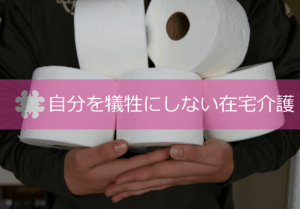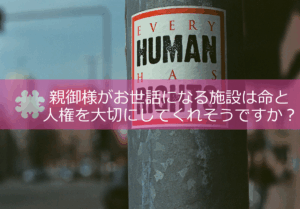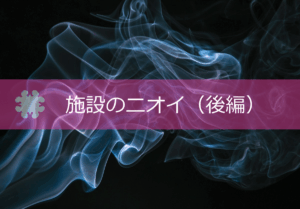2025年7月の参議院議員選挙が終わりました。投票率が高くないと民意が反映された結果とは言い難いのは、私が言うまでもないことです。
一方で、長寿の方々の投票行動は、総務省の年代別投票率をみると70代以上で括られてしまっています。年齢を重ねるほど、投票行動も大変になるのが現実ですが、在宅介護ではキチンと支援していく必要があります。なぜなら、
投票権を勝ち取った歴史を検証すれば、支援は当然との思いに至ります。
女性参政権
日本のムーブメントは大正デモクラシーあたりですが、実際に国政への女性参政権は第2次世界大戦後に認められます。
ごく最近と言えば、最近であり、今でこそ当たり前に感じるかもしれませんが、当たり前ではなかったのです。
そのため、私の周辺では、戦前生まれのご長寿の女性の選挙への意識は非常に高いです。
私が在宅で介護をする以前から選挙の投票行動について、実母は「義務」だ、と常々申しておりました。
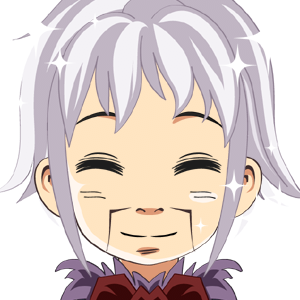 さくらの母
さくらの母選挙に行くのは義務だよ。
これは、権利を主張したのだから、義務も生じる、この当たり前の認識が投票行動を支えます。
そのため、昭和の時代は投票率は、70%を超えるのが普通でした。
戦前、戦中、そして戦後の苦しい時代において、次の世代によりよい形でこの国を継いでいかせるために、ひとりひとりがその責任を感じている時代でもありました。
在宅介護をすると、その責任感は言葉にならなくても伝わってくるものです。
認知症でも投票ができるのか?
私の家庭の例ですが、在宅介護をしている時も選挙を迎える時は、親子で議論が盛んになります。
認知症でも、候補者の主張を聞き、だれに投票するのか。
その意志決定は、当然、支援があれば問題なくできます。
まず、認知症は悪化を防げますし、なにもかも判らなくなってしまう病気ではありません。
アルツハイマー型認知症では、まず短期記憶にダメージが出てきます。
物忘れ等々です。
ここでよく考えてみて欲しいのです。
物忘れが激しくても、個人の政治に対する考え方、主張は忘れたりはしません。
認知症でも、昔のことはよく覚えているといった現象には遭遇するはずです。
選挙の候補者に一票を投じるにも、候補者の根底にある主義、主張を理解するのに短期記憶のダメージは影響しません。
ですから、候補者ごとの主張について、親子でよく話し合う機会をもつという、どこか理想的な家庭になってしまうのが在宅介護のメリットといえるでしょう。
選挙前に、親と子で候補者の主張について議論するご家庭はそう多くないように見受けています。
ただ、いわゆる泡まつ候補や、新人で無所属だったりすると、興味、関心は薄まります。
特に、東京では候補者が多くなるので、どうしてもこれまでの党名、党勢へのイメージが先行するのは否めません。
一方で、東京都知事選のような一騎打ち的な様相を呈する選挙は、介護支援の必要なく投票したい候補者は決まります。
例えば、2016年の都知事選(小池さん、増田さん、鳥越さんの選挙戦)は、候補者の人数が少なく、支援団体や主張が判りやすく、私と母で推したい候補が違いますから、バトル的な議論が勃発します。
こうなると、在宅介護で支援するのは、投票日と、投票所への道のりだけです。
投票所に到着して、立会人の方に支援を求めれば、必要な対処はしてくださるので、無事に投票を済ませることができます。
認知症でも責任感は消えません
責任感は、机上の勉強で培うものではありません。
もっといえば、脳の記憶でどうにかするようなものでもありません。
幼いころから、培っているものです。
どこに培うのか。
それは、心です。
ですから、認知症になったとしても、責任感は消えないのです。
介護する子は、その責任感を発揮させるように支援するのがポイントです。
選挙だけに限りません。
普段から、同居している家族の一員として、頑張るところを頑張ってもらう。
認知症を患っていても、家族の一員として責任を果たしている実感をもってもらうのは、在宅介護の要諦です。
私の在宅介護では、同居する家の精神的支柱として頑張ってくださいと、認知症の母にお願いしていました。
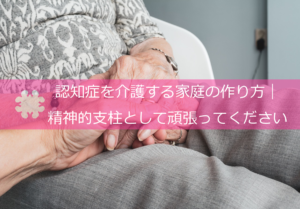
これがベースにあるから、選挙で誰に投票するのか、その議論も、投票行動も一緒に実現できます。
年齢を重ねたんだから、なにもやらずに、ただただ隠居するように為すべきことを取り上げるのは、在宅介護ではありません。
たとえ年老いて認知症を患ったとしても、家族の一員として、責任を果たすための行動をとりやすいにように支援する。
ここが大事です。
今では、70歳以上と括られてしまった年代の投票率ですが、75歳の人と、95歳の人では選挙の投票に対する意識は違うように見受けます。あくまでも私が感じてきた実感です。
戦前生まれの方々がこれから少なくなり、戦後生まれの方々がどこまで先人の意志を継いでゆけるのか。
どの時代も、劣化していく先に新たな時代が幕開けとなるのが歴史の教科書には記されています。在宅介護は、自分の生きていない時代にイマジネーションを働かせて温故知新する行為です。
権利を放棄したり、他人に委ねるのだけはやってはいけません。