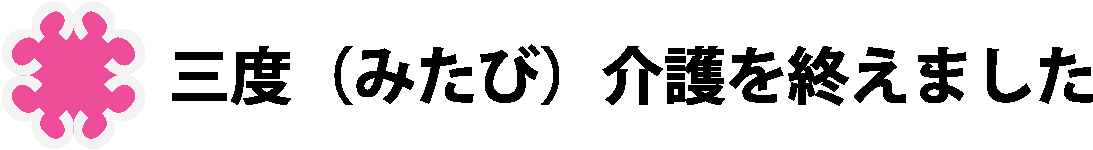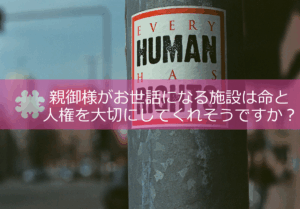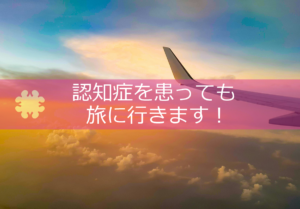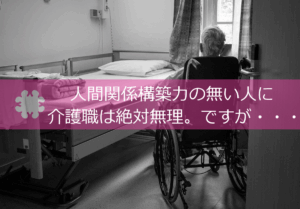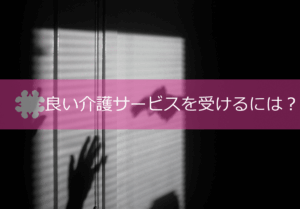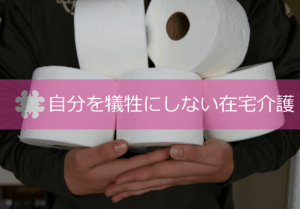月に一度、ケアマネさんが自宅に訪問してくれて、私の母、そしてキーパーソンである私の3人で、近況を共有します。特養のショート・ステイ(1泊)から戻ってきてから、ケアマネさんの自宅訪問まで、そう時間は空かなかったように覚えています。
なので、母も記憶が鮮明です。
認知症なのに記憶が鮮明?
不思議に思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。
正確には、強く動かされた感情はそう簡単に消えないのです。だから、認知症でも激しく動いた感情に伴う記憶は覚えています。
ご存じないですか?
そうなんです、感情と記憶は密接な関係があるのですが、そこにも触れながら、ケアマネさんに伝えたクレームについて紹介していきましょう。
感情と記憶の関係
ほとんどの人は、感情と記憶の関係を知らないのです。
だから、認知症ケアをいくら学んだところで、認知症症状を表面化させない取組は成功しません。
言われている認知症ケアは、行動への対処のみですからね。
そもそも、記憶と感情は密接にリンクしています。
それを次の記事にまとめているので、参考にしてみてください。
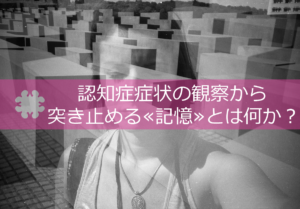
ケアマネさんに特養のショート・ステイについて報告
今回の特養のショート・ステイについて、そのサービスを受けるにあたって、ケアマネさんが尽力してくれました。
当時は、それだけショート・ステイの需要が高かったのです。
しかし、だからといってこの度の母の恐怖体験について、議論をしないわけにはいきません。
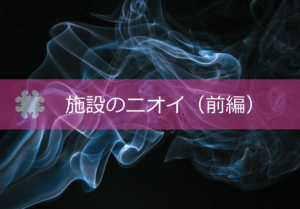
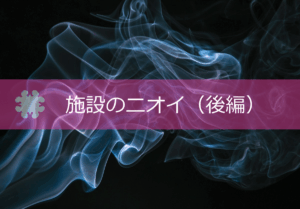
担当のケアマネさんに、母は、自分の恐怖体験を自分の言葉で伝えます。
認知症なのに、なぜ覚えているのか不思議に思う方もいらっしゃるかもしれませんね。
でも、感情が記憶のインデックスになっているのです。
今回は恐怖ですが、その強さがあればあるほど、記憶は定着します。
ケアマネさんも、丁寧に謝ってくださるのですが、しかし、原因に対してアプローチするのが難しいのです。
例えば、今回の母が経験した恐怖体験を特養に伝えたとしましょう。
改善すると思いますか?
改善なんかするわけがないのです。
施設内を徘徊する他の利用者の行動を抑制するには、拘束するしかありません。
ただ、拘束は現実的に不可能です。
他にも、センサーや、監視カメラで、異常行動をセンシングするやり方はいくらでもあります。
センサーが起動したら、職員が駆けつける、なんていうのは机上のお話です。
夜間のスタッフの人数が少ない時に、同時多発的に生じる困りごとに、毎日キッチリと対応しきれないのが現実です。
ですから、母が体験したことは、体験したこととして「仕方がない」と割り切るしかありません。
申し訳ない気持ちが我慢を強いる
施設でも、高齢者虐待はフツーに起こります。
例えば、赤ちゃん言葉で高齢者に接する職員もいます。
利用者の認知症が深刻だと発語も不自由になりますから、虐待を受けていたとしても家族に訴えることができません。
そのため、家族が隠しカメラを設置して証拠を掴んで、そこまでして施設を訴えたという話も聞きます。
基本的に、利用者の家族としては、年老いた親御様を施設に預かってもらうことに「迷惑をかけて申し訳ない」という感情を抱きがちです。
私も、ある日、デイサービス施設に母を預かってもらっている時に、体調が急に悪化して、母が施設内で嘔吐したことがあります。
施設の方々にはご迷惑をかけたと思い、その次の日には差し入れを持参するといった行為はしました。もちろん、施設の方々は軽々には受け取りませんが、それでもということで受け取ってもらったりはしていました。
またある施設は、盆暮れの品が多く届き、それが当然というところもあります。
他にも、地方にいけば、人的ネットワークは狭いですから、子供同士のつながりで、お友達の親が施設長だったりして、そこに自分の親を預けていると安心ではあるけれども、何かあってもクレームは言えない、という現実もあるのです。
どうです?介護サービスを受けるにしても、そう簡単ではない現実があるのです。
私の介護サービス利用選択の経験で、失敗した一つが特養のショート・ステイです。失敗を踏まえてハッキリしたのですが、介護サービスを利用する上でもっとも重要なのは利用に向けた考え方です。
在宅介護は、施設に任せるのではなく、自分が実現しなくてはいけない在宅介護に向けて、介護サービス提供者、事業者にどう協力してもらうのか。
その明確化がポイントです。次の記事では、このポイントについて解説していきます。