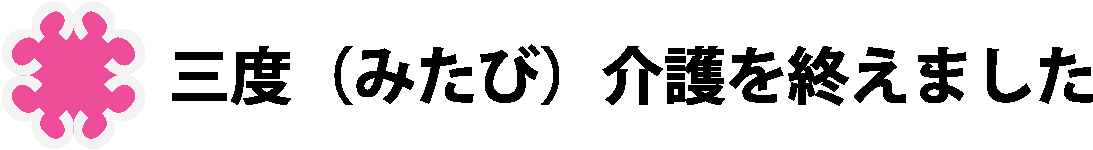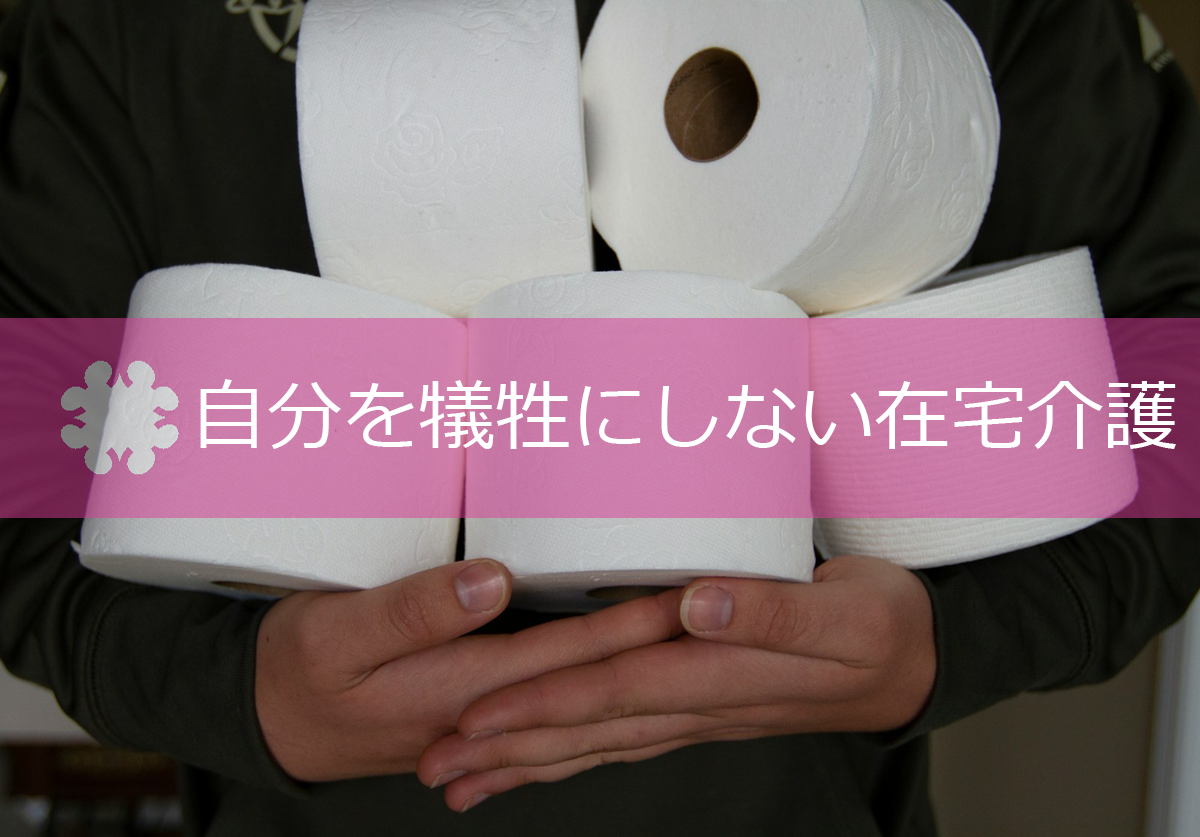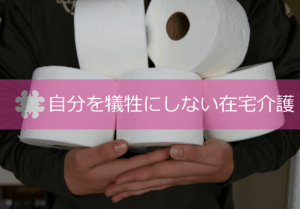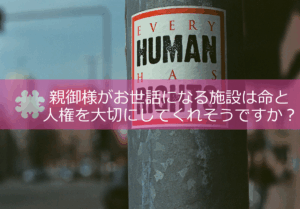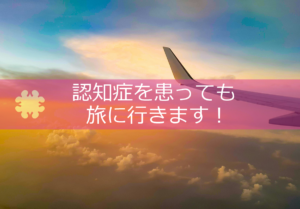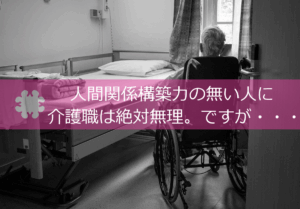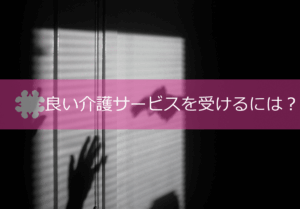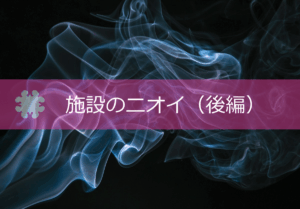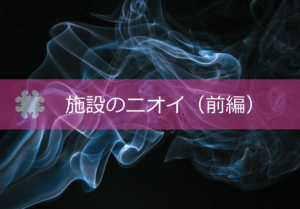年老いた親御様を在宅で介護する責任を担う方、主に子の方からの相談をよく受けます。
相談を受けるからには、そこに問題や、課題が存在するわけですが、実はその問題や課題の根底にあるものは、ほとんど共通しています。もちろん、私のこれまでの在宅介護経験でも共通しています。
なんだと思いますか?
その答えは、実はシンプルで、親と子の人間関係です。
この関係性を善くできれば、実は在宅介護は、とても楽しくなります。
その逆はとても苦しいのです。
親御様の在宅介護が始まる前の抵抗感
年老いた親御様も、70代に差し掛かるか、その前後ぐらいはお元気に自立した生活を営んでいらっしゃる場合は多いかもしれません。
最近は、その割合も徐々に増えていらっしゃるのではないでしょうか。
ただ、転倒による怪我や、病気によって、看護、介護を必要とする親御様もいらっしゃることでしょう。
一方で、子の立場からすると、親御様が心配である旨のコメントはよく耳します。
耳にしますが、でもそこで終わっている場合も多いように見受けます。
そのため、親御様が看護や、介護が、いざ必要となってから言葉だけだった心配が具体性を帯びて、どうにかしなくてはいけない、と動き出します。
でも、ここで多くの子にとって、気持ちの中で抵抗感が生じます。
『親のトイレを介護するなんて、できるのか・・・?』
そんな気持ちを抱く場合もあるでしょう。
でも、より奥深くに横たわる乗越えなくてはいけない感情もあるのです。
『いまさら、親と一緒に住めないし・・・。』
そもそも、一日、2日の里帰りとはわけが違う状況に直面するわけです。
それでも在宅介護は始まります
時間は待ってくれません。
コンロの火をつけっぱなしにして、あやうく火事になりかけた、そんな親御様の生活状況を無視するわけにはいきません。
ですから、急きょ、同居というケースも少なくないわけですが、ここで最初にハードルを感じるのが親と子の人間関係です。
実は、この人間関係に悩む方が、多いのです。
例えば、親御様が総入れ歯をお使いで、メンテナンスがしっかりとされていないと汚れがつきやすいです。
そこへ、認知症が加わると、義歯洗浄をご自分でできないという状況にも遭遇します。
ところが、介護をする子が、義歯を洗浄するから外してほしいとお願いするとしますよね!?
親御様は、子のリクエストに素直に従ってくれると介助も楽ですが、そう簡単には子の云う事を拒否する状況にも遭遇するはずです。
他にも、リハビリパンツ、杖、車いす、補聴器といった、介助用品を導入する際にも、親御様は拒否を示される場合も多くあります。
これ、実は、親御様との人間関係の構築に問題解決の鍵があるのです。
お互いに甘えから感謝の関係に
実は、親と子の関係で、親御様が認知症を患っていたとしても早期の段階から介護をしていけば、コミュニケーションは保たれていきます。
発語が出来なくなっても、目で気持ちが通じ合うといったことも可能です。
ですから、親御様が認知症になっても早期から介護をするように心がけるべき、というのが私の考えでもあるのですが、そのうえで、親も、子も、それぞれの立場になって気持ちを見つめる、というプロセスがとても大事になってきます。
例えば、親御様にリハビリパンツを着用してもらうシチュエーションをとりあげます。
リハビリパンツは、排泄を失敗してしまっても、衣類や、寝具等々への汚れを最小限に食い止めてくれる、とても機能的な下着です。
では、このリハビリパンツを介護している子が、ぜひ、履いてみていただきたいのです。
できれば、思い切って、排泄してみていただきたいのです!
実は、まず、出来ないと思います。
嫌だな、という抵抗感はすさまじいものがあると思います。
年老いた親御様だって、認知症を患っているとしても、その抵抗感は同じです。
それを、履いてもらわなくてはいけないわけです。
一方で、介護する子にしてみれば、確かにリハビリパンツを履いてもらえれば介護は楽になりますが、それ以前に、親御様と同居して介護している本心は、親に対して、安全に、安心して、健やかに過ごしてほしい気持ちがあってこそのはずです。
しかし、親にしてみたら、そこまでの気持ちが判っていたとしても、子への感謝には至らない。
親と子の間に、そんなギャップがあるわけです。
そこで、とるべき行動は、介護の責任を持つ子が年老いた親御様に、ご自分の本心を打ち明けていく必要があります。
「なぜ、親御様の介護をしたいのか?」
もちろん、親御様のご健康と安全・安心を願ってのことですから、その心の内をありのままに親御様に打ち明ける。
実は、親子だから分かり合えている、親は子の気持ちを判ってくれていると思ったら大間違いです。
お互いに判っているようで、判っていません。
この心の内を披瀝していくところが、ご自分を犠牲にしない介護の出発点です。
年老いた親御様の在宅介護は、子が一方的に介助作業で人生の時間を撲殺されていく滅私奉公ではありません。
親も、子も、心の内を打ち明けて、お互いに理解を深めていくプロセスです。
決して、目に見える形ではありません。しかし、心を成長させてくれるプロセスとなります。その実感は、在宅介護を経験してみて判ります。
そして、深まるだけ深まるとそのプロセスは、親御様が最期を迎えて終焉です。
挑戦しない手はありません。